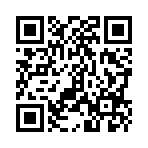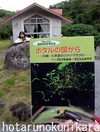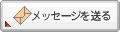2007年12月27日
甲羅に穴を開けられたカメ
今までも、何度か、リュウキュウヤマガメを、持ち込まれたことがありましたが、
どの個体も、大好物のミミズを与えると喜んで食べてくれました。
「なんだか、変ねぇ。」
「そうだね、しばらく様子を見てから、山に放しに行くことにしよう。」
よく見ると、甲羅には、小さな丸い穴が開けられて、鼻の近くに深い傷があります。

ダニがついている様子も無く、もしかしたら誰かが飼育していたのかもしれません。
リュウキュウヤマガメは、雑食性で、ミミズだけでなく、カタツムリや
この時期に熟して落ちるシナノガキなどの実も大好きです。




もちろん、ミカンやリンゴなどの果実も大好きです。
動作の遅い陸上のカメたちは、
獲物を襲って餌を獲得することは苦手ですが、雑食になることで、餌の種類を広げ
その上、鳥や動物の腐乱した死骸でも、食べることが出来る丈夫な胃袋を持つことで、
大昔から現在まで、長く生きながらえることができたのです。
方言では、ヤマガーミー(山の亀)とか、
ヤンバルガーミー(ヤンバル〔沖縄本島北部〕のカメ)と呼ぶこともあって、
リュウキュウヤマガメの生息地は、沖縄本島の北部がよく知られていますが、
それ以外は、この久米島と、渡嘉敷島だけにしか生息していません。

世界的にも、この3ヶ所の島にしか生息していない貴重なカメです。
環境庁(現環境省)編纂の『日本版レッドデータブック』でも、
危急種―絶滅の危険が増大している種―に挙げられ、
沖縄県版レッドデータブックでは、絶滅危惧種(ⅠB類)に掲載されています。
そのため、多くの研究者や、小さな頃から愛着を持ってカメを見てきた
ウチナァーンチュにとっても、その生存が大変心配されています。
今後は、『種の保存法』による指定も検討されなければならないでしょう。

保護されたヤマガメは、数日すると、右目が膿み始め、動きも鈍くなってきました。
右前足の甲羅に開けられた小さな穴の角度から推察すると、
どうやら鼻の横にあった顔の傷は、甲羅に穴を開けるために用いた錐か、
アイスピックなどの先端が刺さって、傷つけられたのかもしれません。

復帰前、私が子どもの頃ですが、カメの甲羅に穴を開けて針金を通し、
庭で飼うことを父から教えてもらったことがあります。
その頃は、何の疑問も持たずに、
カメの硬い甲羅に手際よく穴を開ける父を、尊敬のまなざしで見ていました。
野生の生きものであるリュウキュウヤマガメの、
本来あるべき姿を理解できるようになった今では、
そうした行為を行なうことも、行なわせることも絶対にありませんが、
情報の行き渡っていない小さな島では、まだ、そうした行為の無謀さに気づかないまま
父から子へと、生きものたちとの上手な“付き合い方”ではなく、“取り扱い方”として、
伝授され続けているのではないかと思うのです。
その、“取り扱い”に失敗して、傷ついた生きもの達は、当然のように放置され
そのほとんどは、命を落としてしまいます。
かろうじて、助かった場合でも、
野生復帰することは、過酷なペナルティを背負うことになるでしょう。


これまでに何度も穴の開けられたカメを保護してきました。いずれも命からがら逃げ出したものと思われます。
良識のある人間なら、こうした時代の終わりを理解し決別することができますが
今でも、こうした甲羅に穴の開いたカメや、
メジロを捕獲するためのトリモチや落とし籠を目にする度に
経済優先で進めてきたために起きた環境破壊で、生きもの達の激減している
今の島の現状に目を背け、過去の豊かな自然に抱かれて、
生きものたちがあふれるほど身近に存在していた頃の感覚を、
かろうじて生存している島の生きものたちに無理やりはめ込み
“知恵の伝承”という隠れ蓑に潜んで、酔いしれる人々の空しさを、心から悲しく感じます。
こうした人々からその取り扱いを伝授された子どもたちを
子どものしていることだからという“免罪符”で、放置し続けてしまえば、
その被害は、物言えぬ小さな地球の仲間たちを絶滅へ追いやることに
手を貸すことになるのです。

幼い頃に培われた生きものたちへの間違った対応は、大人になっても、
なかなか払拭することはできません。
それでも、多くの人々が、その行為の間違いを指摘し、声を上げることで、
未来の地球環境の姿を、明るく希望に満ちた状況へと導くことができます。
これからの時代、野生の生きものたちが身近に見られる環境は、
昔の人々からすれば、信じられないほど、多くの付加価値を持つことになります。
沖縄という島に存在していた本来の魅力は、人と、生きもの達の共有する
自然環境の豊かさに裏付けられた、生命への限りないやさしさだと信じています。
「元気になりますように。」と願いながら水を代えて、餌を取替え続けて数日後
リュウキュウヤマガメは、想いが通じたように、膿んで腫れた右目が治り、
持ち上げると勢いよく手足をばたつかせるようになりました。
こんな奇蹟は、万に一つも無いかもしれませんが、私の手にゆだねられた、
人間よりもはるか昔からこの島に生存していたリュウキュウヤマガメの
小さいけれど大切な自然の命の、逞しい生命力に深い感銘と、感謝が溢れます。

温かな日差しの合間から、ヤマガメの大好きな雨が、
「おつかれさま。」と言ってくれるように、やさしく、降り注いできました。


↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
申し訳ないのですが、もし可能であれば2つともクリックして応援をお願いします!

どの個体も、大好物のミミズを与えると喜んで食べてくれました。
「なんだか、変ねぇ。」
「そうだね、しばらく様子を見てから、山に放しに行くことにしよう。」
よく見ると、甲羅には、小さな丸い穴が開けられて、鼻の近くに深い傷があります。

ダニがついている様子も無く、もしかしたら誰かが飼育していたのかもしれません。
リュウキュウヤマガメは、雑食性で、ミミズだけでなく、カタツムリや
この時期に熟して落ちるシナノガキなどの実も大好きです。




もちろん、ミカンやリンゴなどの果実も大好きです。
動作の遅い陸上のカメたちは、
獲物を襲って餌を獲得することは苦手ですが、雑食になることで、餌の種類を広げ
その上、鳥や動物の腐乱した死骸でも、食べることが出来る丈夫な胃袋を持つことで、
大昔から現在まで、長く生きながらえることができたのです。
方言では、ヤマガーミー(山の亀)とか、
ヤンバルガーミー(ヤンバル〔沖縄本島北部〕のカメ)と呼ぶこともあって、
リュウキュウヤマガメの生息地は、沖縄本島の北部がよく知られていますが、
それ以外は、この久米島と、渡嘉敷島だけにしか生息していません。

世界的にも、この3ヶ所の島にしか生息していない貴重なカメです。
環境庁(現環境省)編纂の『日本版レッドデータブック』でも、
危急種―絶滅の危険が増大している種―に挙げられ、
沖縄県版レッドデータブックでは、絶滅危惧種(ⅠB類)に掲載されています。
そのため、多くの研究者や、小さな頃から愛着を持ってカメを見てきた
ウチナァーンチュにとっても、その生存が大変心配されています。
今後は、『種の保存法』による指定も検討されなければならないでしょう。

保護されたヤマガメは、数日すると、右目が膿み始め、動きも鈍くなってきました。
右前足の甲羅に開けられた小さな穴の角度から推察すると、
どうやら鼻の横にあった顔の傷は、甲羅に穴を開けるために用いた錐か、
アイスピックなどの先端が刺さって、傷つけられたのかもしれません。

復帰前、私が子どもの頃ですが、カメの甲羅に穴を開けて針金を通し、
庭で飼うことを父から教えてもらったことがあります。
その頃は、何の疑問も持たずに、
カメの硬い甲羅に手際よく穴を開ける父を、尊敬のまなざしで見ていました。
野生の生きものであるリュウキュウヤマガメの、
本来あるべき姿を理解できるようになった今では、
そうした行為を行なうことも、行なわせることも絶対にありませんが、
情報の行き渡っていない小さな島では、まだ、そうした行為の無謀さに気づかないまま
父から子へと、生きものたちとの上手な“付き合い方”ではなく、“取り扱い方”として、
伝授され続けているのではないかと思うのです。
その、“取り扱い”に失敗して、傷ついた生きもの達は、当然のように放置され
そのほとんどは、命を落としてしまいます。
かろうじて、助かった場合でも、
野生復帰することは、過酷なペナルティを背負うことになるでしょう。


これまでに何度も穴の開けられたカメを保護してきました。いずれも命からがら逃げ出したものと思われます。
良識のある人間なら、こうした時代の終わりを理解し決別することができますが
今でも、こうした甲羅に穴の開いたカメや、
メジロを捕獲するためのトリモチや落とし籠を目にする度に
経済優先で進めてきたために起きた環境破壊で、生きもの達の激減している
今の島の現状に目を背け、過去の豊かな自然に抱かれて、
生きものたちがあふれるほど身近に存在していた頃の感覚を、
かろうじて生存している島の生きものたちに無理やりはめ込み
“知恵の伝承”という隠れ蓑に潜んで、酔いしれる人々の空しさを、心から悲しく感じます。
こうした人々からその取り扱いを伝授された子どもたちを
子どものしていることだからという“免罪符”で、放置し続けてしまえば、
その被害は、物言えぬ小さな地球の仲間たちを絶滅へ追いやることに
手を貸すことになるのです。

幼い頃に培われた生きものたちへの間違った対応は、大人になっても、
なかなか払拭することはできません。
それでも、多くの人々が、その行為の間違いを指摘し、声を上げることで、
未来の地球環境の姿を、明るく希望に満ちた状況へと導くことができます。
これからの時代、野生の生きものたちが身近に見られる環境は、
昔の人々からすれば、信じられないほど、多くの付加価値を持つことになります。
沖縄という島に存在していた本来の魅力は、人と、生きもの達の共有する
自然環境の豊かさに裏付けられた、生命への限りないやさしさだと信じています。
「元気になりますように。」と願いながら水を代えて、餌を取替え続けて数日後
リュウキュウヤマガメは、想いが通じたように、膿んで腫れた右目が治り、
持ち上げると勢いよく手足をばたつかせるようになりました。
こんな奇蹟は、万に一つも無いかもしれませんが、私の手にゆだねられた、
人間よりもはるか昔からこの島に生存していたリュウキュウヤマガメの
小さいけれど大切な自然の命の、逞しい生命力に深い感銘と、感謝が溢れます。

温かな日差しの合間から、ヤマガメの大好きな雨が、
「おつかれさま。」と言ってくれるように、やさしく、降り注いできました。

↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
申し訳ないのですが、もし可能であれば2つともクリックして応援をお願いします!

Posted by satou-n at 23:48│Comments(5)
│ホタルとつながる生きもの達
この記事へのコメント
知らない世界を分り易く教えて貰い有難うございました。
生き物をご縁として生きた記憶が無いのですが、少し誘惑にかられるような気持ちもしています。
人間としてもっと真面目に生きたいなという気持ちを改めて持ちました。
生き物をご縁として生きた記憶が無いのですが、少し誘惑にかられるような気持ちもしています。
人間としてもっと真面目に生きたいなという気持ちを改めて持ちました。
Posted by Hbar at 2008年02月02日 20:41
Hbarさん、コメントありがとうございます。
生きもの達への関心を、少しでも持っていただけたなら、幸いです。
人間の世界は、様々に複雑で、移り変わりも激しいものですから、
それだけでも、十分なのかもしれません。
ただ、日々の暮らしのささやかな安らぎや、心のきらめきの核になるものを
じっと追い求めるとき、私たち人間が、『生きる』ために欠かすことができない
のは、自然という存在と、その構成者である生きもの達だと思うのです。
そうした、人間以外の存在への尊厳を、きちんと保つことは、とても大切だと考えていますし、真面目に生きることは、とても楽しい生き方だと思います。
生きもの達への関心を、少しでも持っていただけたなら、幸いです。
人間の世界は、様々に複雑で、移り変わりも激しいものですから、
それだけでも、十分なのかもしれません。
ただ、日々の暮らしのささやかな安らぎや、心のきらめきの核になるものを
じっと追い求めるとき、私たち人間が、『生きる』ために欠かすことができない
のは、自然という存在と、その構成者である生きもの達だと思うのです。
そうした、人間以外の存在への尊厳を、きちんと保つことは、とても大切だと考えていますし、真面目に生きることは、とても楽しい生き方だと思います。
Posted by satou-n at 2008年02月05日 00:57
はじめまして!
先日、子供たちと水族園に行き、そこの亀たちの何匹かが甲羅に大量の穴が開いていました。
理由が知りたくて検索していて、訪問させていただきました。
亀を見たとき、とても痛々しくて悲しい気持ちになりました。
家でも、亀を6匹飼っていますが、旅行から帰ってからは、子供たちは、亀の世話を一生懸命するようになりました。
子供ながらに何か感じる所があったのだと思います。
家で飼っている亀は、外来種なので、最後まで大切に育てていこうと改めて感じました。
ありがとうございました。
先日、子供たちと水族園に行き、そこの亀たちの何匹かが甲羅に大量の穴が開いていました。
理由が知りたくて検索していて、訪問させていただきました。
亀を見たとき、とても痛々しくて悲しい気持ちになりました。
家でも、亀を6匹飼っていますが、旅行から帰ってからは、子供たちは、亀の世話を一生懸命するようになりました。
子供ながらに何か感じる所があったのだと思います。
家で飼っている亀は、外来種なので、最後まで大切に育てていこうと改めて感じました。
ありがとうございました。
Posted by smilemanma at 2013年08月10日 16:25
smilemanma さん、コメントをありがとうございます。
子ども達が、飼育されているカメたちのお世話を一生懸命している事を、本当に嬉しく想います。
痛々しい姿を見ることは、子どもたちにとっては、胸の重い事ですが、そこから学び取る勇気があれば、本当に良い育みがあります。
子どもたちの成鳥が楽しみですね!
子ども達が、飼育されているカメたちのお世話を一生懸命している事を、本当に嬉しく想います。
痛々しい姿を見ることは、子どもたちにとっては、胸の重い事ですが、そこから学び取る勇気があれば、本当に良い育みがあります。
子どもたちの成鳥が楽しみですね!
Posted by satou-n at 2013年08月10日 22:12
at 2013年08月10日 22:12
 at 2013年08月10日 22:12
at 2013年08月10日 22:12初めまして、ミドリガメを飼っているおばあさんです。
排卵期になると散歩に出たがりますので、山に連れて行くのですが、目を離せないので、昨年(甲羅の端っこは爪のようなものなので大丈夫だと思い)甲羅の端にドリルで小さい穴を開けました。
きわの方に開いた直径2~3ミリの小さい穴でしたが、出血してとても後悔しました。幸い1か月ほどで出血は止まりました。
あんなに小さな穴でも出血したのに、写真のように大きな穴や顔の傷ならすごく出血したと思います。元気になって本当によかったですね。
人間のエゴで穴を開けたこと、亀だから痛くても声も出せなかったのに、本当にかわいそうなことをしたと後悔しています。
今度はリードの付けられる服を作ろうかと思います。
リュウキュウヤマガメ、初めて見ました、とてもかわいいですね。
貴重な画像、自然への暖かい感謝の気持ちをありがとうございました。
排卵期になると散歩に出たがりますので、山に連れて行くのですが、目を離せないので、昨年(甲羅の端っこは爪のようなものなので大丈夫だと思い)甲羅の端にドリルで小さい穴を開けました。
きわの方に開いた直径2~3ミリの小さい穴でしたが、出血してとても後悔しました。幸い1か月ほどで出血は止まりました。
あんなに小さな穴でも出血したのに、写真のように大きな穴や顔の傷ならすごく出血したと思います。元気になって本当によかったですね。
人間のエゴで穴を開けたこと、亀だから痛くても声も出せなかったのに、本当にかわいそうなことをしたと後悔しています。
今度はリードの付けられる服を作ろうかと思います。
リュウキュウヤマガメ、初めて見ました、とてもかわいいですね。
貴重な画像、自然への暖かい感謝の気持ちをありがとうございました。
Posted by 夢生の別荘 at 2016年07月09日 15:43
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。