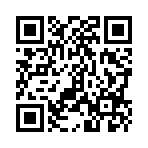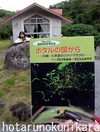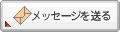2018年06月16日
誘惑のホタル籠
久米島ホタル館には、10数年前に
琉球大学風樹館の佐々木先生から頂いた、テリハボクのホタル籠があります。

テリハボクの実を、丁寧にくり貫いた後、細かな穴をあけて作ります。
一度、挑戦してみましたが、穴がすぐにつぶれてしまい、頂いた見本の様にはできません。
それでも、この小さなホタル籠を手にすると、実際に使ってみたい誘惑に駆られてしまいます。
今の時代には、籠に入れることのできるホタルの数も少なくて、気が引けてしまうというのに、
昔の人の巧みな手業の道具は、使ってこその価値という魔法がかけられているのです。
先人の知恵から生み出され、生活を支えてきた手業の道具は、
失ってしまうには、本当にもったいないものが沢山あります。
その想いは、素直な想いであり、とても大切な想いです。
だからこそ、その純粋な想いが、汚されないように、
伝統文化や工芸を継承するための、自然環境との関わり方や向き合い方を、
真剣に切実に捉え、資源の枯渇を想像しながら、細やかな配慮を願うばかりです。
久米島でも、里山管理の目的で、木を伐りだし、昔使っていた道具を復活させる話がありますが、
正直、今の時代に利用していない道具を形ばかりに数点作り出したとしても、
それは、本当の里山の利用ではなく、木を切って使うための詭弁の様にしか思えません。
里山の管理が必要なのは、その山の自然が里の人々の暮らしに欠かせない事が大事です。
そして、昔の道具を、復活させるには、その道具を活用するための自然再生の方を重視し、
国民の税金で賄われる補助金も、自然再生のために使われてこそ、生き金になると想います。
なのに、”自然再生”という言葉を飾りの様に使う、本末転倒の自然利用のための詭弁ばかりが、
いつの間にか素晴らしい事のように膨らんでしまい、私たちの税金である大切な補助金は、
なかなか、一生懸命に本気の努力をしている人間の手には渡らないのです。

雨上がりの森の中を歩いていると、スズミグモの複雑な巣が、足元で揺れていました。
下から屈んで見上げると、蜘蛛の巣で織り込んだ傘のように見えます。
獲物を捕らえる蜘蛛の巣も、ホタルを捉えるホタル籠も
自然が豊かであればこそ、生かされる美しい造形として、私の胸に迫ってきます。
 久米島ホタルの会体験プログラム
久米島ホタルの会体験プログラム




↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
クリックの応援、ありがとうございます!
琉球大学風樹館の佐々木先生から頂いた、テリハボクのホタル籠があります。

テリハボクの実を、丁寧にくり貫いた後、細かな穴をあけて作ります。
一度、挑戦してみましたが、穴がすぐにつぶれてしまい、頂いた見本の様にはできません。
それでも、この小さなホタル籠を手にすると、実際に使ってみたい誘惑に駆られてしまいます。
今の時代には、籠に入れることのできるホタルの数も少なくて、気が引けてしまうというのに、
昔の人の巧みな手業の道具は、使ってこその価値という魔法がかけられているのです。
先人の知恵から生み出され、生活を支えてきた手業の道具は、
失ってしまうには、本当にもったいないものが沢山あります。
その想いは、素直な想いであり、とても大切な想いです。
だからこそ、その純粋な想いが、汚されないように、
伝統文化や工芸を継承するための、自然環境との関わり方や向き合い方を、
真剣に切実に捉え、資源の枯渇を想像しながら、細やかな配慮を願うばかりです。
久米島でも、里山管理の目的で、木を伐りだし、昔使っていた道具を復活させる話がありますが、
正直、今の時代に利用していない道具を形ばかりに数点作り出したとしても、
それは、本当の里山の利用ではなく、木を切って使うための詭弁の様にしか思えません。
里山の管理が必要なのは、その山の自然が里の人々の暮らしに欠かせない事が大事です。
そして、昔の道具を、復活させるには、その道具を活用するための自然再生の方を重視し、
国民の税金で賄われる補助金も、自然再生のために使われてこそ、生き金になると想います。
なのに、”自然再生”という言葉を飾りの様に使う、本末転倒の自然利用のための詭弁ばかりが、
いつの間にか素晴らしい事のように膨らんでしまい、私たちの税金である大切な補助金は、
なかなか、一生懸命に本気の努力をしている人間の手には渡らないのです。

雨上がりの森の中を歩いていると、スズミグモの複雑な巣が、足元で揺れていました。
下から屈んで見上げると、蜘蛛の巣で織り込んだ傘のように見えます。
獲物を捕らえる蜘蛛の巣も、ホタルを捉えるホタル籠も
自然が豊かであればこそ、生かされる美しい造形として、私の胸に迫ってきます。
 久米島ホタルの会体験プログラム
久米島ホタルの会体験プログラム



↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
クリックの応援、ありがとうございます!
Posted by satou-n at 11:06│Comments(2)
│ホタルの里作り
この記事へのコメント
毎日、久米島ボタルのマンホールを踏んづけて歩いているのに、”久米島ホタル”を見たことがある島民がどのくらいいるだろうか…。沖縄本島から移住してホタル館を立ち上げ運営している館長夫妻の努力には頭が下がる思いでいっぱいだ。先頭を行く人は、不屈の人だと思う。
”久米島ホタル”の乱舞する時期は終わったけれど、来年は多くの人に見に来てほしいと思う。暗夜、そこかしこに乱舞するホタルを見たら感動しますよ!
”久米島ホタル”の乱舞する時期は終わったけれど、来年は多くの人に見に来てほしいと思う。暗夜、そこかしこに乱舞するホタルを見たら感動しますよ!
Posted by 海の見える家 at 2018年06月22日 09:09
ありがとうございます。
コメントに、涙しています。
コメントに、涙しています。
Posted by satou-n at 2018年06月22日 10:24
at 2018年06月22日 10:24
 at 2018年06月22日 10:24
at 2018年06月22日 10:24※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。