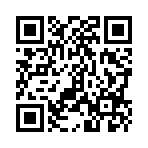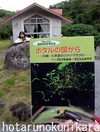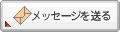2011年11月24日
第1回久米島町民俗芸能大会
プログラムは、文化協会古典部会の幕開けから始まり、
民俗芸能保存功労者表彰式が、華やかな舞台で行われました。

そして、主催者の挨拶や久米島町長の祝辞の後、久米島核集落に今も伝わる
貴重な民俗芸能の踊りが、それぞれの地域の方々により繰り広げられました。
兼城伝統芸能保存会の白瀬走川節で、二白と赤の貫花を肩にかけ、
花笠と、紅型の艶やかな衣装を纏った二人の踊り手の姿に、
沖縄の古典的な踊りの「貫花」が、直ぐに浮かびました。

私が高校生の頃の文化祭で、クラスの女子と一緒に「貫花」を踊った事があります。
その時に、みんなで作った小物が、白と赤の貫花でした。
受付の時に頂いたパンフレットに、白瀬走川節が、その「貫花」の原型とみなされていると
書かれていて、”なるほど!”と、納得すると同時に、琉球絣の発生だけでなく、
ウチナーの歴史に名を残す久米島の、琉球王府時代から引き継がれてきた奥深さに、
触れる事が出来た感動は、自分の中のなつかしい思い出と絡まり、
長年の謎が解けたように爽快で、本当に衝撃的でした。

ゆっくりとした古典の調べから、一転して、現代口調で、テンポが良く、
息の合った見事な園舞で、会場をわかせたのは、久米島紬音頭保存会でした。
踊り手の一人にはホタルの会の藤田さんのお母さんも居られます。
振付のパターンを変えながらも、要所要所で、見事に一致した動きにメリハリがあり、
手の返しだけでも、数パターンの動きが、とても軽やかで、会場からは、
「あんし、上手やる」(すごく、上手ねぇ)と、感嘆の声が上がっていました。

一緒に行った6年生の息子と、パンフレットに書かれている踊りの解説を読んで、
一番面白そうだったのが、兼城伝統芸能保存会の『しゅんどー』でした。
解説によれば、この『しゅんどー』は、有名な獅子舞、白瀬走川節と共に、
兼城の三大伝統芸能として、受け継がれているそうです。

二人の美女の踊りに負けじと、醜い二人の女性が踊り比べをするという内容から、
『しゅんどー』の『しゅん』には、醜(しゅう)みにくいという字が充てられていたのかしら?と、
踊りの名前を想像し、醜い踊り手って、いったい誰がその役をするのかしら?、
ちょっとかわいそうじゃないかしら?と、息子と二人で、演目の解説を読むだけでも、
ワクワクしたり、人を思いやったりと、会話の弾む楽しい気持ちになりました。

そして、実際に出て来た醜女は、変な顔のメイク?か、お面をした男性でしたし、
醜女の踊りには、”笑われてかわいそう”という、憐みよりも、”笑いをとってなんぼです。”の
強かさがにじみ出ていたので、私と息子は、心おきなく大きな声で、笑う事が出来ました。

仲泊民俗芸能保存会の『体操浜千鳥』も、大真面目な、にーせーたー(青年達)の
踊りというよりは、体操の様な、ぎこちない素ぶりに、会場は、大爆笑でした。

そして、さすがと感じたのは、玉城流でだの会の家元、玉城千枝先生の黒石森城節。
赤いてぃさーじ(手ぬぐい)を、振りながら、掛け声と共に踊る余裕に
「すごいなぁ~」の一言です。



古典民謡大会代表の唄い手の二人の声は、艶のある美しい声で、うっとりしてしまいました。

もう、これは、プロだよね!と、想ったのは、兼城伝統芸能保存会の獅子舞です。
メーモーイ(前踊り)の女性の滑らかな手の動きに、惹きつけられていると、
妖怪のような仕草の二人が出てきて、その後を、獅子がついてきます。
ジャンジャンと迫力のあるドラの音色も、本当によかったです!

そして、圧巻だったのは、最後の演目、大原エイサーでした。


大太鼓のない、地味な振付のエイサーに、会場の皆さんの、感謝の気持ちが重なり
何とも言えない満ち足りた気持ちになりました。


出演者の皆さん、関係者の皆さん、楽しい夜を、ありがとうございました



↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
クリックの応援、ありがとうございます!
民俗芸能保存功労者表彰式が、華やかな舞台で行われました。

そして、主催者の挨拶や久米島町長の祝辞の後、久米島核集落に今も伝わる
貴重な民俗芸能の踊りが、それぞれの地域の方々により繰り広げられました。

兼城伝統芸能保存会の白瀬走川節で、二白と赤の貫花を肩にかけ、
花笠と、紅型の艶やかな衣装を纏った二人の踊り手の姿に、
沖縄の古典的な踊りの「貫花」が、直ぐに浮かびました。

私が高校生の頃の文化祭で、クラスの女子と一緒に「貫花」を踊った事があります。
その時に、みんなで作った小物が、白と赤の貫花でした。
受付の時に頂いたパンフレットに、白瀬走川節が、その「貫花」の原型とみなされていると
書かれていて、”なるほど!”と、納得すると同時に、琉球絣の発生だけでなく、
ウチナーの歴史に名を残す久米島の、琉球王府時代から引き継がれてきた奥深さに、
触れる事が出来た感動は、自分の中のなつかしい思い出と絡まり、
長年の謎が解けたように爽快で、本当に衝撃的でした。

ゆっくりとした古典の調べから、一転して、現代口調で、テンポが良く、
息の合った見事な園舞で、会場をわかせたのは、久米島紬音頭保存会でした。
踊り手の一人にはホタルの会の藤田さんのお母さんも居られます。
振付のパターンを変えながらも、要所要所で、見事に一致した動きにメリハリがあり、
手の返しだけでも、数パターンの動きが、とても軽やかで、会場からは、
「あんし、上手やる」(すごく、上手ねぇ)と、感嘆の声が上がっていました。

一緒に行った6年生の息子と、パンフレットに書かれている踊りの解説を読んで、
一番面白そうだったのが、兼城伝統芸能保存会の『しゅんどー』でした。
解説によれば、この『しゅんどー』は、有名な獅子舞、白瀬走川節と共に、
兼城の三大伝統芸能として、受け継がれているそうです。

二人の美女の踊りに負けじと、醜い二人の女性が踊り比べをするという内容から、
『しゅんどー』の『しゅん』には、醜(しゅう)みにくいという字が充てられていたのかしら?と、
踊りの名前を想像し、醜い踊り手って、いったい誰がその役をするのかしら?、
ちょっとかわいそうじゃないかしら?と、息子と二人で、演目の解説を読むだけでも、
ワクワクしたり、人を思いやったりと、会話の弾む楽しい気持ちになりました。

そして、実際に出て来た醜女は、変な顔のメイク?か、お面をした男性でしたし、
醜女の踊りには、”笑われてかわいそう”という、憐みよりも、”笑いをとってなんぼです。”の
強かさがにじみ出ていたので、私と息子は、心おきなく大きな声で、笑う事が出来ました。

仲泊民俗芸能保存会の『体操浜千鳥』も、大真面目な、にーせーたー(青年達)の
踊りというよりは、体操の様な、ぎこちない素ぶりに、会場は、大爆笑でした。

そして、さすがと感じたのは、玉城流でだの会の家元、玉城千枝先生の黒石森城節。
赤いてぃさーじ(手ぬぐい)を、振りながら、掛け声と共に踊る余裕に
「すごいなぁ~」の一言です。



古典民謡大会代表の唄い手の二人の声は、艶のある美しい声で、うっとりしてしまいました。

もう、これは、プロだよね!と、想ったのは、兼城伝統芸能保存会の獅子舞です。
メーモーイ(前踊り)の女性の滑らかな手の動きに、惹きつけられていると、
妖怪のような仕草の二人が出てきて、その後を、獅子がついてきます。
ジャンジャンと迫力のあるドラの音色も、本当によかったです!

そして、圧巻だったのは、最後の演目、大原エイサーでした。


大太鼓のない、地味な振付のエイサーに、会場の皆さんの、感謝の気持ちが重なり
何とも言えない満ち足りた気持ちになりました。


出演者の皆さん、関係者の皆さん、楽しい夜を、ありがとうございました



↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
クリックの応援、ありがとうございます!
Posted by satou-n at 22:50│Comments(0)
│沖縄のこと世界のこと
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 の舞台を堪能することが出来ました。
の舞台を堪能することが出来ました。