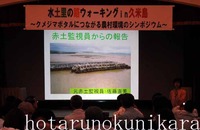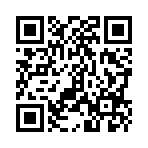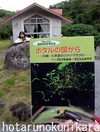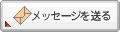2013年03月12日
久米小赤土探検隊のベチバー植え
その植物は、本当は、何でも構わないのですが、
グリーンベルトとして植えた植物の種が、畑に広がってしまう事を理由に
なかなか協力者が得られないため、町の産業振興課では、
種をつけない外来植物のベチバーを栽培し、
農家の畑からの赤土流出防止対策に役立てようとしています。

そうした折、5年生の担任の先生が、子ども達の赤土探検隊の活動の締めくくりに、
これまで、ホタル館の館長と一緒に調査し、
地域のお年寄りたちの思い出深い、やまだ橋の川に影響する畑地で、
赤土流出防止のグリーンベルト対策に同意してくださる農家さんと畑、
ベチバーの苗の提供を産業振興課にお願いして、今回の作業に至りました。

久米島小学校の子ども達は、この日のために、学校敷地内の小さな畑で、役場から分けて頂いた
ベチバーの苗を、大きな株に育てて収穫し、植え付け用に株分けをして
バケツ5杯分のグリーベルト用の苗を準備していました。


役場の方の案内で、到着した畑では、
役場と連携して赤土流出防止対策を行なっている海を守る会のみなさんも
待機されていたので、久米島小学校の先生や子どもたちは、これまで
”赤土流出を減らすために学んできた事を、
多くの人が望む、正しい事として捉える”自信になったようでした。

しかし、赤土流出を防止するために本気で向き合うための対策作業は、
まだまだ、始まったばかりです。

実際、グリーンベルト対策で、赤土流出を防止する有効な範囲は、
側溝から1メートルほど植えこまなくてはいけないのですが、役場の担当者は、
株が大きく成長し、ススキに良く似た葉っぱが、壁の様に生えそろうので、
側溝と畑の間に、横一列に植えるだけで良いと言います。

また、どんな植物も、植えた後の数日間は、水やりの必要性があるのですが、
それも、「大丈夫!」の一言で済まされてしまいました。

ベチバーを植えるために、むき出しにされた斜面には、もともと、ススキや春の一年草が、
生えていたのですが、それらは、刈り取られて畑の片隅に積み重ねられていました。

「この草も、抜いたほうがいいの?」と、その風景を不思議に想った女の子が
斜面に僅かに残った雑草を指差して質問しました。
「いいえ、本来は、そうして自然に芽生えた植物たちが、
畑の赤土流出を防止する役目を果たしているから、この草は抜いちゃダメだよ、
私たちがこうして植えているベチバー達と一緒に、
この畑の土を、川や海に流さないために頑張ってもらおうね。」と答えると、
小首をかしげながらも、その子は、私の目を真っ直ぐに見つめてくれました。

赤土流出を防止するためにと、ベチバーを植えること、今はまだ、それで良いのだと想いました。
でもそれだけが総てでは無い事も、伝えています。
植えた植物を大切に育てる事、自らの畑の土を、雨で流して失わない様にする事、
それは、いったい、誰のためなのか、何のためなのか・・。
今はまだ、赤土流出問題を悩んでいる過程の中にいて、
子ども達は、いずれ、必ず、何が正しいのかに、気づいてくれると信じています。
久米島の自然を守りたいという素直な想いは同じでも、そのために必要な配慮が、
人の都合や事情を優先させる方に傾きつづけていては、
いつまでたっても、多くの人が望む、本物の島の自然は、海の豊かさは、戻りません。

『赤土を畑から流してはいけない!』という発想に真剣に向き合い
人の生き方が、自然の仕組みや生きものへの大きな負担とならないように
工夫する事や、その行為自体を、未来の地球再生へ向かう生きた証として
喜びと感じる事が出来た時、
私たちは、真の幸福を得る事が出来るのかもしれません。




↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
クリックの応援、ありがとうございます!
グリーンベルトとして植えた植物の種が、畑に広がってしまう事を理由に
なかなか協力者が得られないため、町の産業振興課では、
種をつけない外来植物のベチバーを栽培し、
農家の畑からの赤土流出防止対策に役立てようとしています。

そうした折、5年生の担任の先生が、子ども達の赤土探検隊の活動の締めくくりに、
これまで、ホタル館の館長と一緒に調査し、
地域のお年寄りたちの思い出深い、やまだ橋の川に影響する畑地で、
赤土流出防止のグリーンベルト対策に同意してくださる農家さんと畑、
ベチバーの苗の提供を産業振興課にお願いして、今回の作業に至りました。

久米島小学校の子ども達は、この日のために、学校敷地内の小さな畑で、役場から分けて頂いた
ベチバーの苗を、大きな株に育てて収穫し、植え付け用に株分けをして
バケツ5杯分のグリーベルト用の苗を準備していました。


役場の方の案内で、到着した畑では、
役場と連携して赤土流出防止対策を行なっている海を守る会のみなさんも
待機されていたので、久米島小学校の先生や子どもたちは、これまで
”赤土流出を減らすために学んできた事を、
多くの人が望む、正しい事として捉える”自信になったようでした。

しかし、赤土流出を防止するために本気で向き合うための対策作業は、
まだまだ、始まったばかりです。

実際、グリーンベルト対策で、赤土流出を防止する有効な範囲は、
側溝から1メートルほど植えこまなくてはいけないのですが、役場の担当者は、
株が大きく成長し、ススキに良く似た葉っぱが、壁の様に生えそろうので、
側溝と畑の間に、横一列に植えるだけで良いと言います。

また、どんな植物も、植えた後の数日間は、水やりの必要性があるのですが、
それも、「大丈夫!」の一言で済まされてしまいました。

ベチバーを植えるために、むき出しにされた斜面には、もともと、ススキや春の一年草が、
生えていたのですが、それらは、刈り取られて畑の片隅に積み重ねられていました。

「この草も、抜いたほうがいいの?」と、その風景を不思議に想った女の子が
斜面に僅かに残った雑草を指差して質問しました。
「いいえ、本来は、そうして自然に芽生えた植物たちが、
畑の赤土流出を防止する役目を果たしているから、この草は抜いちゃダメだよ、
私たちがこうして植えているベチバー達と一緒に、
この畑の土を、川や海に流さないために頑張ってもらおうね。」と答えると、
小首をかしげながらも、その子は、私の目を真っ直ぐに見つめてくれました。

赤土流出を防止するためにと、ベチバーを植えること、今はまだ、それで良いのだと想いました。
でもそれだけが総てでは無い事も、伝えています。
植えた植物を大切に育てる事、自らの畑の土を、雨で流して失わない様にする事、
それは、いったい、誰のためなのか、何のためなのか・・。
今はまだ、赤土流出問題を悩んでいる過程の中にいて、
子ども達は、いずれ、必ず、何が正しいのかに、気づいてくれると信じています。
久米島の自然を守りたいという素直な想いは同じでも、そのために必要な配慮が、
人の都合や事情を優先させる方に傾きつづけていては、
いつまでたっても、多くの人が望む、本物の島の自然は、海の豊かさは、戻りません。

『赤土を畑から流してはいけない!』という発想に真剣に向き合い
人の生き方が、自然の仕組みや生きものへの大きな負担とならないように
工夫する事や、その行為自体を、未来の地球再生へ向かう生きた証として
喜びと感じる事が出来た時、
私たちは、真の幸福を得る事が出来るのかもしれません。




↑できるだけ多くの人に読んでいただこうとエントリーしています。
クリックの応援、ありがとうございます!
Posted by satou-n at 19:43│Comments(0)
│赤土について
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |